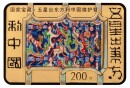「自虐ネタ」で中国人の笑いを取る異色の日本人女性―中国メディア
拡大
北京で暮らす外国人が増加している。その多くが、外国語の教師や企業の上級管理職、ビジネスマンなど。そんな中、他の外国人とは少し異なる仕事に就いている日本人がいる。
(1 / 2 枚)
北京で暮らす外国人が増加している。その多くが、外国語の教師や企業の上級管理職、ビジネスマンなど。そんな中、他の外国人とは少し異なる仕事に就いている日本人がいる。新華網が伝えた。(文:于壮)
【その他の写真】
「相声(中国式漫才)」を学ぶ外国人は多いが、中国語を使ってトークショーを行う外国人はほとんどいない。日本人の近松貴子さんは、中国語でトークショーができる数少ない外国人の一人だ。近松さんは一見してすぐに日本人と思わせるようなタイプではない。第一印象はまるで中国の大学生のように見える。綿のシャツを着た姿は清潔で知性ある雰囲気を漂わせている。しかし近松さんが舞台に立つと、日本人のたくましさと精神を感じることができる。
外国人がトークショーを行うには、いくつかの難関をクリアしなければならない。まずは言葉の壁。トークショーには決まったセリフなどなく、聴衆が聞いて全て理解できるように話さなければならない。近松さんの中国語は外国人の中では特にずば抜けてうまいというわけではないが、ステージで話す際の言葉遣いや話すスピードをうまく把握している。聴衆全員にしっかりと聞いてもらうように心がけているので、一部の中国人パフォーマーよりも話す言葉は明瞭だ。
2つ目は文化の壁。トークショーでは一言で聴衆を笑わせなければならない。その一言の裏には豊富な文化的背景を含ませており、聴衆は語り手が何を風刺しているのか、余計な解説を加えなくてもわかりあえるからだ。これは要するに「笑いのツボ」だ。私たちが外国のコメディーを見ても笑いのツボが理解できないように、外国人にとってもまた私たちの笑いのツボを理解するのは難しい。「時には苦労して考え付いた話をしても、全く反応がなかったこともありました」と近松さんも笑いのツボを理解する難しさを痛いほど感じている。「ステージに上がるのはたった1分でも、その裏には10年もの積み重ねがある」と言われているように、近松さんもステージ上で聴衆を爆笑させるネタを考え出すために、度重なる練習と血のにじむような努力を重ねたことだろう。
3つ目は自虐の壁。トークショーにはいくつか決まりがある。例えば障がい者などの弱者をからかってはいけないが、自虐ネタは問題ない。近松さんが笑いのツボとして使うのも自虐ネタだ。日本人は中国で自虐ネタにできるものが多すぎるほどある。欧米人パフォーマーからすると、自虐は特にめずらしいものではないが、日本や中国といった儒家文化の国は、民族に対する強い自尊心を持っている。もし中国人が日本で中国の不合理な物事をけなして観客の笑いを取ったならば、すぐにネットユーザーの怒りを買い、吊るし上げられてしまうのだろう。近松さんが果敢にもこの一歩を踏み出し、自虐ネタを選んだのは本当に勇気のあることだといえる。一途で、考えを曲げない、自分が正しいと思ったらとことん突き進む、これも実は日本人のあまり知られていない特徴だろう。
例えば近松さんが日本の礼節の煩わしさをネタに「日本人は毎日何度もお辞儀をして、ヨガを思いついたんですよ」と話し、120度のお辞儀をしてみせる。さらに「ヨガはインド人が思いついたものって言われているんですよ。日本のヨガがインドに盗まれてしまいました。でも私たちはこれっぽっちも怒っていません。だって最終的には全て韓国人のものになるんですから」と風刺する。韓国人ネタは中国と日本では広く知られていることなので、観客からは自然と笑いが巻き起こる。
近松さんは若く見えるので、ずっと日本でも中国語を勉強していたのだと思っていた。しかし話を聞いてみると、意外にも日本で中国語を勉強したことはなく、しかも中国に来てまだ2年も経っていないという。私は10年近く日本語を勉強しているが、ステージでのトークショーはおろか、即興スピーチですらまともにできない。
私は近松さんから、外国語を学ぶには天賦の才が必要と言われるが実はなにより勇気が必要なのだと感じた。日本人は保守的な民族だが、著名な探検家もよく誕生している。このような日本人はまだ見ぬ世界を恐れず、自分から飛び込んでいく。近松さんもその一人だ。彼女は日本が制作した清代末期の宮廷を描いたドラマ「蒼穹の昴」を見て、登場人物の魅力に引き込まれ、紫禁城をこの目で見たいという思い、中国に憧れるようになったのだという。そして中国で仕事をする機会があったので、やってきたのだ。
近松さんを見ていると、私はいつも「日本人でありながら中国語でトークショーをしている。私たちも勇気を持って、未知の世界に思い切って飛び込んでみるべきじゃないか。それは本当にそんなに難しいことだろうか。私たちに一歩踏み出す勇気がないだけじゃないだろうか」と思っている。近松さんはいつもトークショーの最後に「私がタクシーに乗るとき、運転手はいつも『あなたは韓国人かい』と聞いてきます。そういうとき私は『棒子(韓国人の蔑称)じゃなくて、鬼子(日本人の蔑称)ですよ』と答えています」と締めくくる。「鬼子」という言い方すら自虐ネタに変えてしまう近松さんは、確実に私たちの間に一歩近づいてきている。(提供/人民網日本語版・編集YK)
レコードチャイナを通じて世の中に発信しませんか?ご連絡はこちらまで
関連記事
中国の「憤青」の暴走が止まらない!ボイコットで墓穴、日本人に難癖、韓国人も「被害妄想」とあきれる始末
Record China
2016/7/21
日本の「神話」は本当か!?実際に行ってみたけど…=中国ネット「中国は犬にも劣るということか」「会社に日本人の社員がいて…」
Record China
2016/7/21
日本の小学生のある光景を中国視察団が絶賛「感慨深かった」―華字メディア
Record China
2016/7/20
日本人はなぜロボット産業に熱くなるのか―中国メディア
Record China
2016/7/21
いったい誰に礼をしているの!?日本のある動画に中国ネット感心=「日本は怖すぎる…」「こんな民族とは戦争したくない」
Record China
2016/7/20